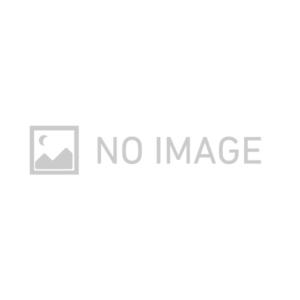鳴子農園は鳴子温泉から車で10~15分程度の場所に位置しておりますので、本日は鳴子温泉郷についてと鳴子温泉郷の歴史について記載させていただきます。
【鳴子温泉郷とは】
鳴子温泉郷は、「鳴子」「東鳴子」「川渡」「中山平」「鬼首」といった5つの温泉地からなり、300近くの源泉があります。
また、泉質の種類も非常に豊富で、11種類の泉質のうち8種類の泉質を持つ全国的にも非常に珍しい温泉地であり、
大分県の別府温泉と並んで全国でも最多となっております。
※私自身、別府(実際は大分市内ですが、、、)と鳴子の両方に住むという温泉好きでもあります
鳴子温泉郷は、昔から湯治場として有名で、温泉の効能や泉質の良さには非常に定評があり、
実際に当地を訪れる観光客の方々とお話しを聞くと泉質の良さや種類の豊富さに魅かれたリピーターが非常に多いです。
【鳴子温泉郷の歴史】
【平安時代】
鳴子温泉の歴史は、837年(承和4年)の鳴子火山の噴火によって、現在の温泉源の多くが誕生したとされ、以後「鳴子温泉」の始まりと伝えられている。
伝説によると、村人が地面から湯が湧き出る音(“なるこ=鳴る子”)を聞きつけ、発見したとも言われています。
【中世〜江戸時代】
鳴子は早くから湯治場として栄えました。
江戸時代には伊達藩の御用温泉にもなり、武士や旅人、農民たちが傷や疲れを癒やすために訪れる場所でした。特に東鳴子温泉は「湯治場」として格式が高く、長逗留の湯治客が多く見られたのが特徴です。
【明治時代】
陸羽東線(鳴子線)が開通し、観光地としてのアクセスが向上したことで、明治以降、鳴子こけしの産地としても知られるようになります。
「鳴子こけし」は東北三大こけしの一つ。湯治客や観光客が「こけし」を土産に買い求めたのが、こけし工芸の発展につながりました。
【昭和時代】
高度経済成長に伴う観光ブームで温泉地としての人気が急上昇。宿泊施設や商店街、観光インフラが整備され、首都圏や関西圏からの観光客が増加。鳴子峡の紅葉はこの頃から全国的な景勝地として知られるようになります。
ちなみに、鳴子温泉郷は大崎市鳴子温泉という住所になりますが、大崎市の由来は足利氏の流れをくむ名門斯波氏一族で奥州管領であった大崎氏からきています。また、鳴子温泉の隣町が大崎市岩出山というのですが、伊達政宗の居城であった岩出山城があり、歴史深い町となってなっておりますので、ぜひ一度ご来訪いただき、歴史を感じながら温泉に入っていただければと思います